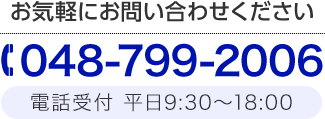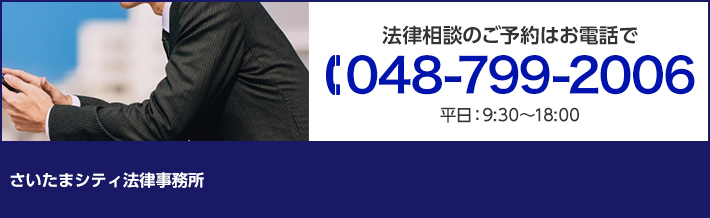1 ADHD(注意欠如・多動症)とは
ADHD(注意欠如・多動症)は、注意力の欠如、集中力の維持が難しい、多動性、衝動的な行動等が特徴の障害です。ADHDは、日常生活や学習において困難を引き起こすことがあります。
当事務所の問題社員対応についてはこちら>>
2 ADHDなど発達障害を理由とした解雇リスク
ADHDなどの発達障害を理由に解雇することには、複数の大きなリスクがあります。言うまでもなく、解雇に関しては厳しい規制されていますし、障害者雇用に関する各種規定においては、事業者に障害を持つ労働者を配慮することを義務付ける内容とっているため、解雇を選択した場合のリスクは極めて大きいものです。具体的なリスクは以下のようなものがあります。
3 不当解雇であると主張されるリスク
これまでの労働裁判例の蓄積により,解雇には合理的な理由が必要であるとのルールができあがりました(解雇権濫用法理)。
| (解雇) 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 |
発達障害を理由に解雇した場合、上記要件に該当せず、違法な不当解雇とみなされる可能性が極めて高いと考えられます。すなわち、発達障害者が適切な支援を受けることなく解雇通告を受けた場合、解雇が差別的な措置とされ、解雇の不当性はより高度であると考えられます。
4 合理的配慮の提供義務違反
平成28年4月に改正障害者雇用促進法が施行され、雇用分野における障害者差別は禁止、そして、合理的配慮の提供は義務とされました。また、令和6年4月に改正障害者差別解消法が施行され、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されています。
このように、企業には障害を持つ従業員に対して「合理的配慮」を提供する義務があります。これは、発達障害を持つ従業員が業務を円滑にこなせるように必要な支援や調整を行うことを意味します。この義務を果たしていない場合、解雇が不当であると評価される可能性が高くなります。
5 レピュテーションリスク
発達障害を理由に解雇することは、企業の社会的な評判(風評)に悪影響を与えることがあります。特に近年、企業の社会的責任やダイバーシティ・インクルージョンの重要性が高まっている中で、障害者を不当に解雇したと認識された場合、企業の社会的なイメージが悪化し、顧客や取引先からの信頼を損なう可能性があります。
6 ADHDなど発達障害を理由とした解雇が認められるケース
発達障害そのものを理由とする解雇が認められるケースは、基本的には「ない」と言って差し支えないでしょう。
もっとも、例えば、重要な書類管理を任されているのにミスが続き、会社の運営に重大な支障をきたすなど仕事の遂行が著しく困難であり、合理的な配慮をしても適切に業務をこなせないケース、企業が適切な配慮(配置転換、業務調整など)を提案したものの、本人がこれを受け入れず、業務遂行が困難であるケース、暴言やハラスメントに該当する行動が繰り返され、注意や改善指導を受けても直らない場合など、発達障害によるコミュニケーションの問題が極端に深刻であり、職場環境の維持が困難になるケース、発達障害に関連して長期間の休職を余儀なくされ、復職の見込みが立たないケースなど、従業員の退職を検討せざるを得ない場面もあろうかと考えられます。
しかし、そのような場合であっても、まずはその従業員に対して退職勧奨(従業員に自主退職を促すこと)を行い、従業員に退職届を提出して、自主的にやめてもらうことができないかを検討するべきです。解雇は、常に「不当解雇トラブル」のリスクがあるため、自主的な退職を促すのが、法的リスクを生じさせない最善の策と言えるでしょう。
7 ADHD などの発達障害の社員に対する会社の適切な対応方法とは
前述のとおり、事業者には発達障害者に対する合理的配慮が求められており、合理的配慮に関しては厚生労働省が指針を策定しており、発達障害も含め、合理的配慮に関する事例集も策定されています
上記の合理的配慮の事例集においては、障害類型別に合理的配慮の内容が策定されています。上記事例集においては、発達障害に関する合理的配慮の一例として、「募集・採用の面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること」、「募集・採用の面接・採用試験について、文字によるやり取りや試験時間の延長を行うこと」、「採用後に業務指導や相談に関し、担当者を定めること。」「採用後に業務指示やスケジュールを明確にし、指示を一つずつ出す、作業手順について図等を活用したマニュアルを作成する等の対応を行うこと。」などが挙げられています(合理的配慮事例集65頁以下)
また、令和5年6月11日付け朝日新聞デジタル版の記事「発達障害の社員が求める配慮「わがままではなく企業成長のチャンス」では、企業の具体的な取り組みが紹介されています(https://www.asahi.com/articles/ASR5S53JCR5PUTFL00L.html)
8 職場環境の構築はさいたまシティ法律事務所にご相談ください
企業に求められる合理的配慮については、法律上の義務とされ、企業には必然的に対応が求められます。一方で、障害者雇用促進法の改正は比較的最近の出来事であり、どのような対応が必要なのか戸惑われている会社も多いことでしょう。
職場環境の構築においてお悩みがあれば、ぜひさいたまシティ法律事務所にご相談ください。
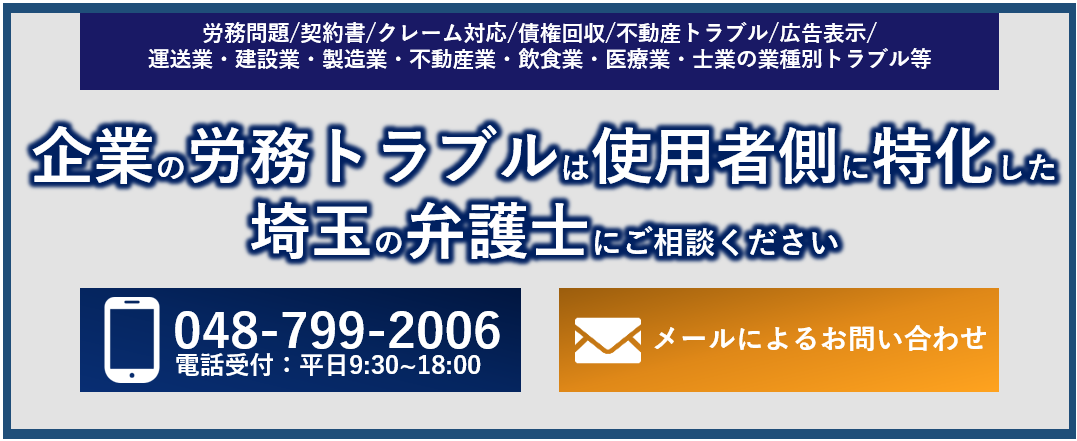
Last Updated on 2025年11月7日 by roumu.saitamacity-law
 この記事の執筆者:代表弁護士 荒生祐樹 さいたまシティ法律事務所では、経営者の皆様の立場に身を置き、紛争の予防を第一の課題として、従業員の採用から退職までのリスク予防、雇用環境整備への助言等、近時の労働環境の変化を踏まえた上での労務顧問サービス(経営側)を提供しています。労働問題は、現在大きな転換点を迎えています。企業の実情に応じたリーガルサービスの提供に努め、皆様の企業の今後ますますの成長、発展に貢献していきたいと思います。 |