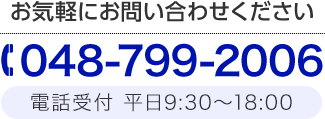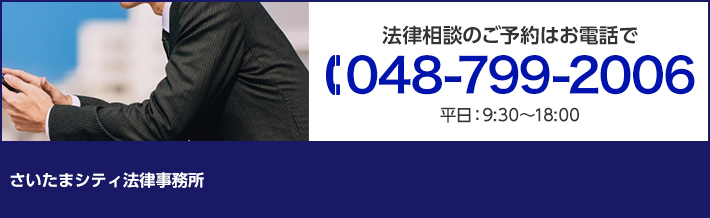能力不足を理由にやめてもらうことはできるのか
能力不足を理由とした解雇に限られず、日本では、従業員の解雇は極めて厳格な法規制が施されており、解雇することは極めて困難です。
| (解雇) 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 |
これまでの労働裁判例の蓄積により、解雇には合理的な理由が必要であるとのルールができあがりました(解雇権濫用法理)。上記の労働契約法第16条は、解雇権濫用法理を明文化したものです。解雇が認められるには、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が求められます。
能力不足を理由とした解雇を検討する際には、特に慎重な対応が必要です。それは、「能力不足」かどうかを客観的に証明することは難しいからです。そもそもどういった「能力」が求められていたのか、能力が不足しているとどういった理由から判断できるのか、経営陣の主観ではなく、あくまで客観的な証明が必要となります。
当事務所の問題社員対応についてはこちら>>
正しい解雇・退職勧奨の手順
前述のとおり、能力不足の社員に対しては特に慎重な対応が求められます。具体的には、定期的な面談、社内外の研修の受講、配置転換、業務日報による業務報告などを通じて、相当期間の指導を行い、改善の機会を提供しなければなりません。これらの過程を経ることなく、いきなり解雇を選択することは悪手です。このような過程を経ることにより、該当の社員との間で、会社として期待する水準、パフォーマンスの悪さを具体的に共有することになります。そのような改善の機会を与え続けてもなお改善がみられない場合、退職に向けたプロセスを検討せざるを得ませんが、それでも解雇の選択肢の前に、少なくとも以下の過程を踏むべきです。
⑴ 指導・注意
能力や適性を欠く問題社員に対しては、まず上司が注意・指導を行い、改善の機会を与えることは必要です。具体的には、本人に対して、業務能力向上のための教育指導を実施します。特に、「いつ」、「誰が」、「どのような」指導を行ったのか、またどのような改善が見られたか等について、メールや指導票などに記録し証拠として残すことが重要です。「会社として教育指導を行い、十分に改善の機会を与えた」という事実は、後に解雇の効力が争われた場合に、解雇の有効性の判断材料として大きなものです。
⑵ 業務の変更・配置転換
注意・指導をしても改善が見られない場合は、別部署に配置転換することを検討する必要があります。例えば、営業職で能力を発揮できないならば、事務職に回すなど、異なる職種に就くことで新たな適性が発揮される可能性があります。
配置転換の検討の際、社員の意向や希望を聴取することは重要ですが、必ずしも、従業員の意向に拘束されるわけではありません。ただし、配置転換は就業規則や雇用契約で定められた人事権の範囲内に限って認められるものです。これらに反する配置転換は、人事権の濫用として無効になります。
特に、特定の業種に就くことを前提に雇い入れたにもかかわらず、全く別の職種への配置転換は、当初から雇用契約等により制限されている可能性があるため、要確認です。
⑶ 退職勧奨
能力不足が著しく、配置転換や懲戒処分を行っても改善しない場合は、退職勧奨を検討することになります。退職勧奨とは、従業員に退職するよう説得し、従業員との合意のもとで退職してもらうことをいいます。
会社が一方的に辞めさせるのではなく、本人との合意のうえで退職してもらうため、トラブルを最小限に抑えることが可能です。ただし、退職勧奨の進め方には要注意です。例えば、長時間・繰り返し行われる執拗な退職要求や、「辞めないなら懲戒解雇する」といった、脅迫的な言動を行うと、退職を強要しており、違法であると評価され、後に損害賠償責任を追及される可能性があります。
⑷ 解雇
解雇を選択する際は、少なくとも上記⑴乃至⑶を全て行う必要があります。⑴乃至⑶を行っていない状況のもとで、能力不足を理由とする解雇はまず認められないでしょう。
能力不足を原因に解雇・退職勧奨を行う場合の注意点
労働基準法上、会社が従業員を解雇するときは、原則として「解雇日の30日以上前に予告すること」が義務付けられています(労基法第20条)。これに従い、解雇日の30日以上前に解雇の予告を従業員にしたうえで解雇日まで勤務してもらうのが「予告解雇」です。
前述の通り、原則として解雇日の30日以上前の解雇予告が義務付けられていますが、30日分の賃金を払うことにより、事前の予告をしていなくてもその日に解雇することができます。このように、解雇を事前に予告せず、解雇を伝えた当日に解雇することを「即日解雇」といいます。このときに支払うことになる30日分の賃金のことを「解雇予告手当」といいます。
このように即日解雇と予告解雇という2種類の解雇方法の違いを踏まえたうえで、いずれかを選択することになりますが、結論としては「特別な事情がない限り即日解雇が望ましい」といえます。理由としては、予告解雇をした場合、当該従業員は会社に対し負の感情を持つことがほとんどであり、他の従業員への悪影響等が考えられます。また、解雇日までの間に会社の機密情報を持ち出されるなどのリスクもあるでしょう。確かに、いきなり解雇してしまうと引き継ぎができないといった問題も考えられますが、実際、予告解雇したケースであっても十分な引き継ぎ等を期待することは現実的には中々困難です。そもそも、引き継ぎなど行って欲しい業務がある場合は、解雇を選択すべきではなく、前述のとおり、退職勧奨を検討すべきでしょう。
場合別!能力不足を理由に解雇・退職勧奨を行う場合の注意点
⑴ 試用期間中の社員
試用期間とは、社員の能力や適性を見極めるための雇用期間をいいます。試用期間中の雇用契約は、解約権の留保された契約であり、試用期間中に能力不足と判断された場合は、この解約権を行使して本採用拒否できる契約であると考えられています。そのため、本採用拒否は、通常の社員に行う解雇よりも認められやすい傾向にあります。
ただし、試用期間といっても雇用契約が成立している以上、本採用拒否は解雇にあたるため、本採用を拒否するには、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」を満たす必要があります。単に勤務成績が一般社員より低いことや、社風に合わないなど、漠然とした理由での本採用拒否は認められない可能性が高いです。このように、決して容易に解雇が認められるわけではないのです。この点は、よく誤解がある点です。
例えば、本採用前の暴力事件への関与の発覚など、採用時には知りえなかった事情の発覚や欠勤・遅刻などの勤務不良の程度が平均的な労働者を下回り改善の可能性がない場合などの理由が必要となります。
そのため、社員の資質を見極めるために、十分な指導や注意改善を行い、定期的な面談をすることが求められると考えられます。
⑵ パート・契約社員
契約社員の解雇については、契約期間の途中での解雇は、よほどのことがない限り違法とされていることに注意が必要です。したがって、契約期間中の解雇は基本的にできない、と考えておいた方が良いでしょう。
労働契約法第17条1項には、契約社員の期間途中での解雇は「やむを得ない事由」がある場合でなければできない、とされています。この「やむを得ない事由」があるとして、期間途中の解雇を認めた判例はごくわずかです。能力不足を理由とする解雇は、経歴詐称等の採用時の虚偽申告を伴うようなものでない限り、「やむを得ない事由」があると評価されることは難しいでしょう。
従って、契約社員の能力面に問題がある場合でも、期間途中での解雇は避け、雇用契約の期間満了のタイミングで次の契約を更新しないことにより雇用を終了することを検討するのが無難です。ただし、その場合も、「雇止め法理」が適用されるため、決して容易に雇用を終了することができるわけではありません。
なお、上記説明は、有期雇用されているパート社員の解雇にもあてはまります。パート社員には期間の定めなく雇用されるパート社員(無期パート社員)と1年契約など期間を定めて有期雇用されているパート社員(有期パート社員)があります。有期パート社員の解雇については、契約社員の解雇と同様のルールが適用されます。一方、無期パート社員の解雇については正社員の解雇と同様のルールが適用されます。
⑶ 中途採用社員
中途採用では、これまでの職歴や特別な業務能力に基づき、即戦力として採用するケースが多いです。例えば、新規事業立ち上げのため、技術者や営業部長などを採用するケースが挙げられます。
特定の能力を前提とした採用では、社員が採用時に期待されたパフォーマンスを挙げられないのであれば、債務不履行の可能性があります。この場合は、新卒者に必要とされるほど教育指導のプロセスを踏まなくても、解雇は正当と判断されやすい傾向にあります。したがって、求められた能力が発揮されていない場合には、契約内容の履行がなされていない(つまり債務不履行)として、退職勧奨を検討します。
ただ、よく問題となるのは、「求められた能力」が採用の時点でどれだけ労使双方の共通認識となっていたか否かです。採用の時点では、直ちに即戦力まで求められていたとは言えないことを理由に、中途採用社員の解雇が無効となった事例があります(東京地裁平成28年8月30日判決・ウエストロー・ジャパン)。
中途採用者の解雇の有効性の判断では、教育指導のプロセスよりも、採用時に業務や役職に必要な能力について具体的に説明したか、必要とされる能力と実際の能力にどの程度の乖離があったか等の点が重視されると考えられます。もっとも、未経験者を中途採用した場合は、最初は仕事ができなくても当然であり、会社側にも育成する努力が求められます。
弁護士に相談するタイミング
さいたまシティ法律事務所では、解雇してよいかどうか、解雇前に集めるべき証拠は何があるか、解雇した場合のリスクがどの程度か、解雇した場合のリスクを減らす方法には何があるか、などの解雇に関する事前相談を企業のお客様から、常時承っています。
解雇トラブルに精通した実績豊富な弁護士が、相談企業の事情を詳細にヒアリングしたうえで、ご相談にダイレクトに回答し、また、リスクを減らすための適切な助言を行います。
弁護士への相談の重要性
以上のとおり、能力不足の社員(ローパフォーマー社員)を放置することは会社にとって深刻な結果を招き、他の社員の意欲等に大きく影響することから、放置することが許されない問題であると言えます。問題社員対応にあたって重要なのは、従業員の問題行動への注意・指導のプロセスであり、これができていないと、その後どのような対応方針を取ったとしてもうまくいかず、逆に、無用な紛争を招いてしまうことがあります。
さいたまシティ法律事務所では、配置転換、懲戒処分、退職勧奨、場合によっては解雇に至るまでのスキームを個々のケースに応じてアドバイスをご提供することが可能です。これにより、トラブルのリスクを最小限にとどめることが可能です。
また、すでに起きてしまった労働問題への対応だけではなく、将来のリスク回避のために現在起きている問題を二度と生じさせないように取り組むことが経営強化につながります。さいたまシティ法律事務所では、問題発生の根本を探求し、就業規則の整備・改善や、実際上の労務運用までリスク回避策を積極的に提案しています。問題社員の対応よりも、問題が発生しない土壌を作ることが、会社や従業員にとって何より望ましいものであり、経営の安定化につながります。
能力不足の社員(ローパフォーマー社員)の対応でお悩みの方はさいたまシティ法律事務所までご相談ください。
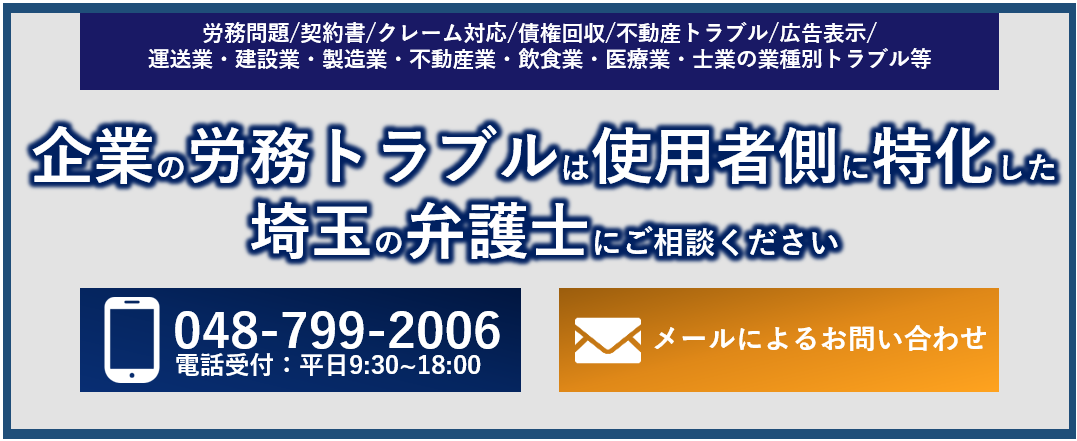
Last Updated on 2025年11月7日 by roumu.saitamacity-law
 この記事の執筆者:代表弁護士 荒生祐樹 さいたまシティ法律事務所では、経営者の皆様の立場に身を置き、紛争の予防を第一の課題として、従業員の採用から退職までのリスク予防、雇用環境整備への助言等、近時の労働環境の変化を踏まえた上での労務顧問サービス(経営側)を提供しています。労働問題は、現在大きな転換点を迎えています。企業の実情に応じたリーガルサービスの提供に努め、皆様の企業の今後ますますの成長、発展に貢献していきたいと思います。 |