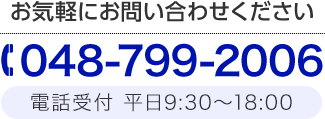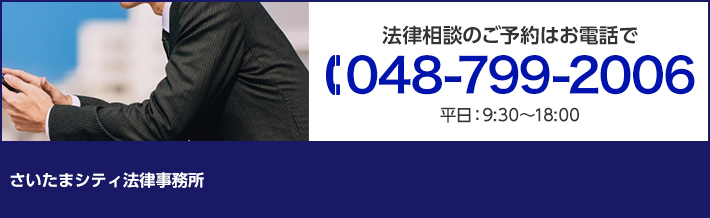指示に従わない、違反する社員にお困りではないですか?
業務に関する指示・命令、時間外労働命令や休日労働命令、あるいは出張命令など、上司の指示・命令に従わなかったり、度々違反する社員にお困りではないでしょうか。このような社員を放置した場合、企業には極めて重大な支障が生じます。
当事務所の問題社員対応についてはこちら>>
指示に従わない社員を放置してはいけない理由
指示に従わない社員を放置すると、他の社員の労働時間・負担が増える、他の社員のモチベーションを低下させる、ハラスメントの被害を受けた社員が退職してしまうといったように、問題社員が存在することにより、他の社員への悪影響は計り知れないものがあります。会社が対応を放置する=容認と捉えられかねず、ローパフォーマー社員からモンスター社員化するおそれがあります。また、放置していると注意指導の証拠も残らず、あとで解雇したいと考えても、会社で必要な指導教育を果たしていないということで解雇は無効となる可能性が極めて高いです。
実際、当事務所に相談に訪れる会社担当者の方が問題社員の対応を求めるのは、「他の社員への悪影響」というこの理由が最も大きいと言っても過言ではありません。従業員は会社の大事な資産ですから、他の従業員に悪影響を与えるということは、会社の生産性の低下、ひいては会社組織そのものの崩壊につながりかねないと言えます。真面目でやる気のある社員が損をするような職場であってはなりません。
問題社員の対応方法(解雇)
1 解雇は極めて困難であること
会社の命令や指示に従わない・違反する社員(会社のルールを守らない)の解雇に限られず、日本では、従業員の解雇は極めて厳格な法規制が施されており、解雇することは極めて困難です。
| (解雇) 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 |
これまでの労働裁判例の蓄積により、解雇には合理的な理由が必要であるとのルールができあがりました(解雇権濫用法理)。上記の労働契約法第16条は、解雇権濫用法理を明文化したものです。解雇が認められるには、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が求められます。
2 解雇の有効性を左右する「客観的に合理的な理由」とは
「客観的に合理的な理由」としては、⑴ 労働者の労務提供の不能や労働能力又は適格性の欠如・喪失、⑵ 労働者の規律違反(経歴詐称、職務懈怠、業務命令違背、業務妨害、職務規律違背)、⑶ 経営上の必要性に基づく理由、⑷ ユニオン・ショップ規定に基づく組合の解雇要求といった内容が典型的な内容として挙げられます(菅野和男「労働法」第十二版・786頁)
3 社会通念上相当と認められるかどうか
社会通念上の相当性とは、労働者が行った行為や状況に照らして、相当な処分といえるか(バランスを欠いていないか)ということを意味します。例えば、軽微な就業規則違反を理由にいきなり解雇したり、これまで一度も懲戒処分を受けたことがなかったり、必要な注意処分や指導教育といった段階を踏まず、いきなり解雇処分としたような場合は、労働者が行った非違行為と解雇とのバランスを欠いているとし、社会通念上の相当性が認められないと判断されることになります。
4 小括
解雇を検討できる場面であっても、会社の法的リスクを最小限にし、また、トラブルを長引かせないようにするためには、解雇は最後の手段ととらえ、まずは退職勧奨により合意による退職を目指すことをおすすめします。従業員を解雇してしまうと、後で不当解雇として訴えられるリスクがあり、その場合、万一敗訴すれば多額の金銭支払い(バックペイ)を命じられます。
問題社員の対応方法(解雇以外の懲戒処分)
1 懲戒処分の種類
懲戒処分一般的には6種類が挙げられますが、ここでは解雇(諭旨解雇も含む)・降格を除く3種類を紹介します。
⑴ 譴責(けんせき)・訓告・戒告
譴責(けんせき)は、文書で厳重注意し、従業員の将来を戒める懲戒処分です。通常は始末書を提出させます。訓告も同様の意味内容で用いられることがありますが、主に公務員において設けられている制度です。戒告は、始末書の提出を伴わない場合が多いようです。
これらはいずれも労基法の概念ではないため、企業によって意味内容が異なることがありますが、いずれも概ね同じ意味であると考えて差し支えないでしょう。懲戒処分としては最も軽いものであり、従業員に対する「指導」を主な内容とし、経済的な不利益を伴うものではありません。
⑵ 減給
従業員の給与を減額する処分です。減給は、労働者保護の立場から法律上の限度額が設けられており、「一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」(労基法91条)とされています。
要するに、1回の問題行動に対する減給処分は、1日分の給与額の半額が限度額であることを意味します。
過去、労基法91条の後段「総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」のみを捉えて、1回の問題行動を対象に、1ヶ月分の賃金の10分の1を減給としたケースに遭遇したことがありますが、このような減給は明らかに違法です。
⑶ 出勤停止
問題行動に対する制裁として、従業員に一定期間出勤を禁じ、その期間の給与を無給とする処分です。出勤停止となる問題行動の典型としては、会社内での暴力行為やハラスメント行為などがあげられます。例えば、30日の出勤停止という場合、30日分の給与が支給されないことになるため(出勤停止の日数のカウントは労働日のみです)出勤停止は減給処分よりも本人が受ける経済的制裁の程度が大きくなります。
なお、出勤停止期間中無休となることは、制裁としての出勤停止の当然の結果であるため、労基法91条の制限を受けることはありません(昭和23年7月3日基収第2177号)。出勤停止の期間は法律上の上限はありませんが、通常は就業規則で上限が決められています。7日や10日程度とされるケースが多いようです。
なお、出勤停止と自宅待機命令の違いが問題となることがよくありますが、出勤停止は懲戒処分であるのに対し、自宅待機は業務命令であり、自宅待機期間中も原則として給与が支払われるという点で違いがあります。自宅待機命令は、問題行動が起こった際、当該従業員を出社させるのは不適当であり、問題行動を調査する必要がある場合などに命じられます。
2 懲戒処分の選び方
懲戒処分は、事案の内容に応じ、本人の弁明も踏まえて適切な処分を選択する必要があります。
軽微な業務命令違反に対して出勤停止処分などの比較的重い懲戒処分を科すことは、不当な
処分として違法になるため注意する必要があります。
3 懲戒処分を科す場合の注意点
懲戒処分を行いうる事情が認められるとしても、適正な手続きを踏まなければその懲戒処分そのものが違法となることがあります。
懲戒は就業規則に書いてあることしかできません。しかし、あらゆる懲戒事由をすべて列挙してあらかじめ記載することは困難であるため、最後に「その他この規則および諸規定に違反し、または前各号に準ずる行為を行ったとき」などの包括条項を定めておくなどの必要もあります。この包括規定があれば、懲戒事由が就業規則に定められていないから処分できない、ということはまず起きないでしょう。
また、労働契約法第15条において、「当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効」とされています(懲戒権濫用法理)。要するに、当該懲戒事由と懲戒処分とのバランスが求められるのであって、例えば1回の暴言で即懲戒解雇とはいかないというわけです。
さらに、1回の問題行動に対し、2回懲戒処分を行うことはできません(二重処罰の禁止)したがって、処分歴のある従業員に再度懲戒処分するに際しては、過去の問題行動を今回の懲戒処分の対象としないように留意しなければなりません。
懲戒処分のいわゆる「相場」の参考としては、一般社団法人労務行政研究所「企業における懲戒制度の最新実態」や人事院「懲戒処分の指針について」(平成12年3月31日職職-68 最終改正令和2年4月1日職審―131)などが参考になるでしょう。
業務命令違反の社員を解雇した裁判例
従業員が、職場内において、再三上司からボイスレコーダーを用いた録音を止めるよう業務命令を受けていたにもかかわらず録音を止めなかったことから、会社側が当該従業員を普通解雇した事案です。この事例では、就業規則では録音禁止が定められておらず、録音禁止の根拠が明確ではありませんでしたが、法人の施設管理権から録音禁止の指示ができること、また、録音禁止は会社の秩序意地のための重要な命令であったとし、一方で、労働者はこれまで複数回業務命令を受けており、譴責処分を受けているにもかかわらず反省の意思を示さず録音を継続した点を捉えて、解雇するにあたり「やむを得ない事由」があると判断しました(東京地方裁判所立川支部平成30年3月28日判決)。
問題社員への対応で注意すべき法的ポイント
1 不当解雇にならないためのポイント
業務命令違反は重大な問題行為であり、懲戒処分を検討することも少なくありませんが、業務命令を下す前に、その根拠・権限があるかどうか(配置転換命令、出向命令等は明確な根拠が必要です)、就業規則や雇用契約書を確認する必要があります。根拠があったとしても、従業員にとってあまりにも不利益が大きい命令や、退職に追い込もうとする目的が透けて見える命令などの場合は人事権行使の濫用となり、その業務命令自体が違法となります。
また、仮に業務命令を拒否された場合、処分等を行う必要がある場合は、その業務命令については書面で明確に行うべきです。書面ではない口頭による命令の場合、そもそもそれが業務命令であったのかどうかといった、無用な争いに巻き込まれることにもなりかねません。
前述の平成30年判決のケースでは、業務命令自体があったことは争いがなかったものの、そもそもそのような命令の発出根拠が争われました。したがって、解雇が有効であるためには、業務命令の根拠があるか否かは勿論、きちんと命令が発出されているか、拒否するにあたって正当な理由がないのか、複数回の業務命令が発せられているにもかかわらず従っていないのか、懲戒処分を受けているのか、といった事情が重視され、そして譴責処分まで経ていることが重視され、逆に、これらの事情なく、1回の業務命令違反でいきなり解雇すると、比例原則違反ということで、解雇は無効となる可能性があります。
2 パワハラ・モラハラにならないためのポイント
学校法人が、入学式や入試などの行事の際に、教員に対して、通学路に立つことを命じた事例について、肉体的負担と精神的苦痛を課してまで実施すべき理由に乏しい上、他の教員との均衡を欠いて集中的に特定の教員に割り当てた点を指摘して、業務命令は違法であるとして、学校法人に対して損害賠償を命じています(東京地方裁判所立川支部平成24年10月3日判決)。
このように、業務命令そのものが不合理な内容の場合、場合によってはパワハラやモラハラに該当する可能性もあります。
企業が就業規則で定めておくべき事項
労働者の業務命令違反を理由に、懲戒処分を行いうる事情が認められるとしても、適正な手続きを踏まなければその懲戒処分そのものが違法となることがあります。
前述のとおり、懲戒は就業規則に書いてあることしかできません。しかし、あらゆる懲戒事由をすべて列挙してあらかじめ記載することは困難であるため、最後に「その他この規則および諸規定に違反し、または前各号に準ずる行為を行ったとき」などの包括条項を定めておく必要があります。
弁護士への相談の重要性
以上のとおり、業務命令違反の社員を放置することは会社にとって深刻な結果を招き、他の社員の意欲等に大きく影響することから、放置することが許されない問題であると言えます。問題社員対応にあたって重要なのは、従業員の問題行動への注意・指導のプロセスであり、これができていないと、その後どのような対応方針を取ったとしてもうまくいかず、逆に、無用な紛争を招いてしまうことがあります。
さいたまシティ法律事務所では、配置転換、懲戒処分、退職勧奨、場合によっては解雇に至るまでのスキームを個々のケースに応じてアドバイスをご提供することが可能です。これにより、トラブルのリスクを最小限にとどめることが可能です。
また、すでに起きてしまった労働問題への対応だけではなく、将来のリスク回避のために現在起きている問題を二度と生じさせないように取り組むことが経営強化につながります。さいたまシティ法律事務所では、問題発生の根本を探求し、就業規則の整備・改善や、実際上の労務運用までリスク回避策を積極的に提案しています。問題社員の対応よりも、問題が発生しない土壌を作ることが、会社や従業員にとって何より望ましいものであり、経営の安定化につながります。
ローパフォーマー社員の対応でお悩みの方はさいたまシティ法律事務所までご相談ください。
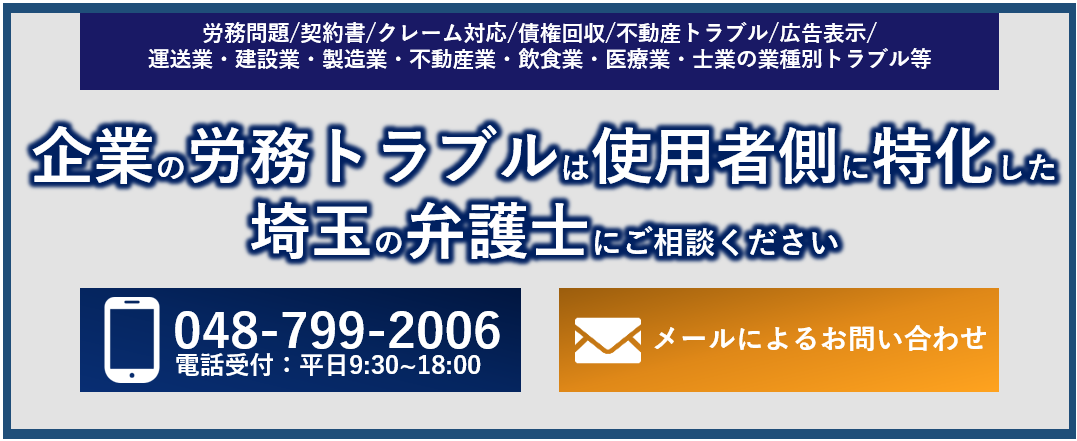
Last Updated on 2025年11月7日 by roumu.saitamacity-law
 この記事の執筆者:代表弁護士 荒生祐樹 さいたまシティ法律事務所では、経営者の皆様の立場に身を置き、紛争の予防を第一の課題として、従業員の採用から退職までのリスク予防、雇用環境整備への助言等、近時の労働環境の変化を踏まえた上での労務顧問サービス(経営側)を提供しています。労働問題は、現在大きな転換点を迎えています。企業の実情に応じたリーガルサービスの提供に努め、皆様の企業の今後ますますの成長、発展に貢献していきたいと思います。 |