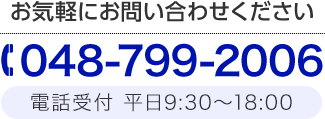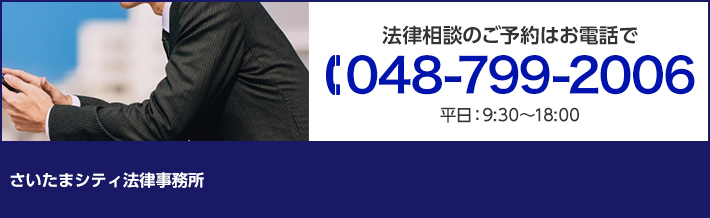就業規則とは
就業規則とは,賃金や労働時間,解雇や懲戒処分の事由,服務規律の内容など,就業にあたり従業員が守るべき規律を定めるものです。合理的な労働条件を定めた就業規則が従業員に周知されている場合,その就業規則は,従業員の個別の同意がなくても雇用契約の内容になります(労働契約法第7条)。就業規則は,多数の従業員の労働条件を統一的に定めるとの点において雇用契約書とは異なる機能をもちます。
就業規則の作成は,常時10人以上の従業員を使用する事業場がある会社においては法律上の義務とされています。労働基準法第89条で,「常時10人以上の労働者を使用する使用者は,就業規則を作成し,行政官庁に届け出なければならない」と定められており,違反した場合には30万円以下の罰金が科されます。
就業規則に関する問題を放置する危険性
就業規則自体がない若しくは就業規則はあっても,労務トラブルや労働審判,労働裁判の現場で役に立たない内容になっているケースが見受けられます。これでは,せっかく就業規則を作成していても機能せず,以下の例のような労務トラブルや裁判で,解決のために多額の金銭を会社側が支払わなければならない結果となったり,従業員の問題行動に対応できず会社が多大な損害を負う場合がありました。就業規則の不備により会社に発生する損害の例としては,以下のようなものが挙げられます。
(例)
(1)就業規則自体が法律に違反しており,損害賠償を請求された
(2)懲戒に関する規定の不備により,従業員に対する懲戒解雇が不当解雇となり,裁判所で多額の金銭支払いを命じられた
(3)機密保持に関する規定の不備により,従業員が会社の情報を持ち出しても適切な対応ができなかった
(4)固定残業代に関する規定の不備により,多額の残業代の支払いを命じられてしまった
(5)就業規則の不利益変更の効力が認められず,多額の金銭支払いを命じられてしまった
就業規則の作成義務について
前述のとおり,労働基準法では常時10人以上の従業員を使用する企業に,就業規則の作成を義務付けています。作成義務の違反には「30万円以下」の罰金が科されます。「常時10人以上」という人数は,「事業所ごと」にカウントします。パートタイマーやアルバイトなど,いわゆる非正規雇用の社員も「10人以上の従業員」に入ります。業務委託社員や派遣労働者,繁忙期のみ勤務する臨時社員は人数に含まれません。
「常時10人以上の従業員」がいない事業所については,就業規則の作成義務はありません。しかし,就業規則はトラブルが起きた場合の会社の拠り所になるものですので,法律上の義務はない10人未満の事業所においても,就業規則を作成しておいた方がよいでしょう。
就業規則の周知について
労働基準法第106条において,「使用者は,就業規則を,常時各作業場の見やすい場所へ掲示し,または備え付けること,書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって,労働者に周知させなければならない。」とされています。
周知がされていない就業規則は多くの裁判例で無効とされていることから,就業規則の作成後に正しく周知することは極めて重要です。例えば,残業を応じる義務を雇用契約書ではなく就業規則で定めている場合,就業規則を周知していなければ,就業規則の効力が認められず,残業を命じる根拠もないことになりますので,注意が必要です。
たまに,社員の過半数代表者等の意見を聞いた上で労働基準監督所に届けてあるから有効だ,という会社がありますが,それだけでは有効ではありませんので,周知の手続きは極めて重要です。
就業規則の周知方法は,労働基準法施行規則第52条の2で定められており,以下のような方法が挙げられます。
ⅰ 各事業所(支社,営業所,店舗など)の見やすい場所に掲示する
ⅱ 書面で従業員全員に交付する
ⅲ 電子媒体に記録し,それを常時パソコンのモニター画面等で確認できるようにする
判例上は,労働基準法施行規則の規定とは別に,就業規則の周知について,実質的に「労働者が就業規則を知ろうと思えばいつでも知り得る状態にしておくことが必要である」とされています。
なお,就業規則を掲示することにより従業員に周知する場合,掲示は事業所ごとに行わなければなりません。本社に行けば就業規則を見ることができるが,支店や支社では見ることができないという場合,支店や支社の従業員に対し就業規則が周知されていたとはいえないことになるため,注意が必要です。
「就業規則の周知」は,就業規則の効力が認められるために必要な重要なポイントです。
就業規則への記載事項について
就業規則の記載事項には,大きく分けて以下の3つがあります。
1.絶対的必要記載事項
就業規則に必ず記載しなければならない記載事項
・始業及び終業の時刻,休憩時間,休日,休暇ならびに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
・賃金(臨時の賃金等を除く)の決定,計算,支払いの方法,賃金の支払いの時期ならびに昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇事由を含む)
2.相対的必要記載事項
制度を設ける場合は必ず就業規則に記載をしなければならない記載事項
・退職金手当の定めをする場合においては,適用される労働者の範囲,退職手当の決定,計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払い時期に関する事項
・従業員に食費,作業用品その他の負担をさせる場合においては,これに関する事項
・安全及び衛生に関する定めをする場合においては,これに関する事項
・職業訓練に関する定めをする場合においては,これに関する事項
・災害補償や業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては,これに関する事項
・表彰及び制裁の定めをする場合においては,その種類及び程度に関する事項
・以上のほか,当該事業場の全従業員に適用される定めをする場合においては,これに関する事項
3.任意的記載事項
就業規則に記載するかどうかが自由である記載事項
(1)採用手続,試用期間,配置転換に関する事項
(2)異動,出向・転籍に関する規定
(3)休暇,服務規律,就業に関する遵守事項に関する規定
そのほかの任意的記載事項としては,
・就業規則の適用範囲に関する規定
・身元保証に関する規定
・業務の過程で発明や著作物の作成があったときの知的財産権の帰属に関する規定
・残業に関する規定
・会社から従業員に損害賠償を求める場合に関する規定
「1.絶対的必要記載事項」及び「2.相対的必要記載事項」は,法律上記載事項が決められています(労働基準法第89条)。
「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」,そして「任意的記載事項」の3つの組み合わせで就業規則が構成されることを,就業規則の作成方法のポイントとしておさえておきましょう。
就業規則の効力について
就業規則の効力は,労働契約法に条文が設けられています。その中で,企業が合理的な労働条件を就業規則に定めて,その就業規則を従業員に周知した場合,就業規則の内容は,企業と従業員の間の労働契約の内容となることが定められています。就業規則の作成は,従業員が一致団結できる組織を作ることが目的であり,「集団」を対象とする点が,雇用契約書との大きな違いです。作成の手続も,雇用契約書が各従業員と個別に取り交わすものであるのに対して,就業規則は事業所ごとに作成するもので従業員の個別の署名捺印は必要ありません。雇用契約書も就業規則もどちらも労働契約の内容となるものですが,雇用契約書が個別の従業員を対象とするものであるのに対し,就業規則は「集団」を対象とするものであることをおさえておきましょう。
雇用契約書と就業規則の内容が食い違うときは,雇用契約書の方が従業員にとって有利な項目については雇用契約書が適用され,就業規則の方が従業員にとって有利な項目については就業規則が適用されるというルールが設けられています(労働契約法第7条但書,労働契約法第12条)。
就業規則の改訂・変更について
一度作成した就業規則も,事業内容の変化や,事業環境の変化,就業条件の変化や法改正などがあったときは,改定,変更することが必要です。変化があったのに,改定しないまま放置することは,就業規則の内容と実際の会社内の就業ルールが矛盾していることになり,企業の労務管理が崩れていく原因になります。 現在,労働関係の法律が頻繁に改正されていることを踏まえると,就業規則も毎年1回は変更が必要になることが通常です。
就業規則の変更には,変更案について従業員代表の意見を聴取した上で,変更届を労働基準監督署に提出し,変更後の就業規則を社内で周知する手続が必要です。また,労働契約法上,原則として,「労働者と合意することなく,就業規則を変更することにより,労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない」(労働契約法第9条)とされている点にも注意が必要です。
パート・アルバイトの就業規則
パート社員や契約社員については,正社員とは労働条件が異なるため,正社員用の就業規則とは別にパート社員用,契約社員用,それぞれの就業規則を作成することが通常です。例えば,パート社員や契約社員について,病気になったときの休職についての扱いや,年次有給休暇の日数,賃金体系などは,パート社員及び契約社員と正社員では異なるのが通常ですので,それを反映した就業規則を作成することが必要です。
また,パート社員,契約社員の就業規則を作成するときは,「同一労働同一賃金ルール」や「雇止め法理」,「無期転換ルール」など非正規社員独自のルールに注意することが重要です。
弁護士による就業規則の作成・見直し
問題のある就業規則の典型として,社内の実情を踏まえておらず,就業規則が形骸化しているケースがあります。最新の法改正や判例の動向が踏まえられておらず,就業規則に効力が認められない条文が含まれているケース,使用者側の一方的な都合や利益のみが強調されており裁判所で効力が認められる可能性がないと思われるケースや,作成後の意見聴取の手続が正しく行われていないケース,就業規則の周知が不十分で,就業規則としての効力が認められないケースなども多く見られます。このような問題のある就業規則では,就業規則がないのと同じであり,労働問題トラブルに対応できず,会社に大きな損害をもたらす危険すらあります。
就業規則は,従業員の問題行動について適切に対応でき,かつ,労働問題トラブル,労働裁判が発生した場合にも会社が正しく対応できる規律であることが必要であり,これらに対応するために,実際に生じた紛争の実情に精通した弁護士による就業規則の作成・見直しが求められます。
弁護士に依頼するメリット
さいたまシティ律事務所では,多くの労働問題や労務トラブル,労働裁判を解決してきた実績があり,その際の経験を生かして,就業規則の内容を,実際の労働問題や労務トラブル,労働裁判にて活用できる内容にするために,常に改善,研究を行っています。このようなことは,実際に裁判を担当して解決にあたる弁護士でなければできません。
さいたまシティ法律事務所に就業規則の作成をご依頼いただくことで,自社の就業規則を実情に沿うものとし,万が一の労務トラブルや労務裁判においても活用することができる内容に整備することができます。ぜひご検討ください。
お問い合わせはこちらから
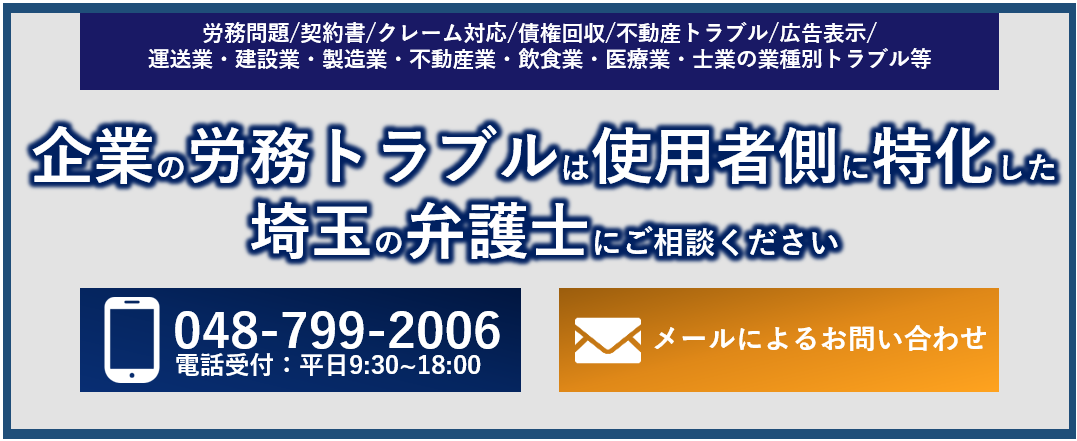
Last Updated on 2024年2月27日 by roumu.saitamacity-law
 この記事の執筆者:代表弁護士 荒生祐樹 さいたまシティ法律事務所では、経営者の皆様の立場に身を置き、紛争の予防を第一の課題として、従業員の採用から退職までのリスク予防、雇用環境整備への助言等、近時の労働環境の変化を踏まえた上での労務顧問サービス(経営側)を提供しています。労働問題は、現在大きな転換点を迎えています。企業の実情に応じたリーガルサービスの提供に努め、皆様の企業の今後ますますの成長、発展に貢献していきたいと思います。 |